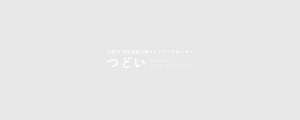つどいでは団体登録のため「定款・会則」の提出を求めていますが、登録を希望される団体であっても、「まだ会則をつくっていません」というケースに出会うことがあります。
お話を聞くと、
「堅苦しくて面倒くさいから後回しにしていた」
「うまく進めているし、仲間に相談したことすらありません」
「必要性を感じないのですが…どうしても作らないといけないのでしょうか?」
というような感じです。
活動をスタートしたばかりで、最初からルールを作るなんて…
なんだか息苦しく感じるかもしれません。
しかし、運営していると様々なことがおきます。
- 新メンバーの加入希望があった
- 仲間と意見が分かれた
- お金の使い道で迷った
- 幽霊部員が数名出てきた
- 助成金を申請しようと思う
そんな場面で、定款・会則の存在が効いてきます。
ルールがあることで不要に悩まず、安心して活動を続けることができるのです。
このページでは、定款・会則の意味と、作るときのコツをお伝えします。
(つどいでも定款・会則の作成を支援しています)
定款や会則は変更もできますから、完璧である必要はありません。
大切なのは、みんなが同じ方向を向いて、目的のために活動できる基盤を作ることです。
とある「料理研究部」の事例を元に考えてみよう
料理研究部で活動するAさんとBさんの事例を通して、定款・会則の意義を想像してみましょう。
春:部活動開始
料理研究部に10人の新入部員が入りました。
最初はみんなで楽しく料理を作っていましたが、少しずつ問題が起きてきました。
- 材料費は誰が払うの?
- 部長は誰が決めるの?
- 活動日はいつ?何時から何時まで?
疑問は出てきますが、その都度みんなで相談して乗り切ります。
活動が中断するのは面倒ですが、そこまで大きな問題には感じられないようです。
夏:混乱の始まり
ある日、来年度の部長選びでもめました。
Aさんは「多数決できめよう」と言い、Bさんは「料理が上手な人がなるべき」と主張します。
他のメンバーも「前の部長が選ぶ」「一番やる気がある人がなるべき」と、まとまりません。
結局、その日は何も決まらず、すこし険悪なムードに…活動も中断してしまいました。
秋:ルールを作ろう
顧問の先生が提案しました。
「最近頭を抱えてばかりで、誰も楽しそうではないですね。よし。料理研究部のルール(会則)を作りましょう。」
「これまで起きたトラブルが、発生しないように。もし発生しても、すぐに解決できるようなルールを考えてみてください」
部員たちは話し合い、以下のようなルール(会則)を作りました。
- 部の名称:⚪︎⚪︎高校 料理研究部
- 部の目的:仲間と楽しく料理を学び、秋の学園祭でオリジナル幕の内弁当を企画・販売する。
- 部長の決め方:翌年度の部長を毎年3月末に全部員の投票で選びます。
- 活動日:毎週火曜日と金曜日の放課後(17時〜19時)欠席は2日前までに申告すること。
- 会費:月500円(材料費、調理機器購入積立金として使います)
- 余剰資金について:翌年度に全額繰り越します。
- 定例会議:毎月第4火曜日は翌月の計画を立てる会議を行います。
- 購入について:3,000円以上の食材・調理機器の購入は定例会議で承認を得ること。
- 入部手続き:部の目的に賛同する方は随時歓迎。入部届けが受理されたら入部できます。
- 退部手続き:退部の7日前までに部長に退部届けを提出してください。
冬:ルールがあることの効果
会則ができてから、部活動がスムーズに運営されるようになりました。
毎月の収入(会費)が計算できるので、先々の予定が立ちます。
学園祭で販売したオリジナル幕の内弁当が好評で、多くの部員を獲得できました。
新しく入部した後輩にも「これが我々のルールだよ」と明確に説明できるようになったのです。
定款・会則の存在意義
1. 混乱を防ぐ「道しるべ」
料理研究部の例のように、ルールがないと「どうしたらいいかわからない」状況が生まれます。
ルールがあることで、迷った時の判断基準ができます。
2. みんなが平等に参加できる「約束」
ルールがあることで、一部の人だけが決定権を持つことを防ぐことが期待できます。
AさんもBさんも、同じルールの下で活動できます。
3. 組織の「アイデンティティ」を示す
「私たちは何のために集まっているのか」
「どんな価値観を大切にしているのか」
を明文化することで、組織の性格がはっきりします。
4. 外部との「信頼関係」を築く
学校側や保護者、地域の人々に「この団体はきちんと運営されている」ことを示せます。
これは特に、予算をもらったり、施設を使わせてもらったりする際に重要です。
5. 問題が起きた時の「解決手段」
もし部員同士でトラブルが起きても、ルールに従って公平に解決できます。
「感情論」ではなく「ルール」に基づいて判断できるのです。
いつの間にかルールに守られている
社会のあらゆる組織においても、同じようにルールが機能しています。
大学のサークルでは会則があることで、新入生がスムーズに活動に参加できます。
会社では定款があることで、株主や取引先との信頼関係を築けます。
地域活動団体では会則があることで、寄付者や行政からの支援を受けやすくなります。
スポーツもルールがないと、トラブルが発生する度に試合が止まってしまいます。
そんな状態では、まったく盛り上がらないですよね?
定期的に見直してみましょう
定款・会則は「みんなが気持ちよく活動するための約束事」です。
明文化されたルールがあることで、組織は安定し、発展し、社会からの信頼も得られます。
あなたの所属する団体に定款・会則はあるでしょうか?
ある場合は、どのようなトラブルを想定しているか、確認してみましょう。
定款・会則は必要に応じて、内容を変更することもできます。
定款・会則がない場合はトラブルを未然に防ぐため、みんなで話し合いを始めてみてください。
定款・会則をうまく使いこなして、目的のために多くの時間を費やせるようにしていきましょう。